
生理学とメカニズム
| アプローチ(1) | アプローチ(2) | アプローチ(3) | アプローチ(4) | アプローチ(5) |
摂食・嚥下障害へのアプローチ(5)
嚥下障害へのアプローチと題して4回にわたり嚥下のメカニズム1) 2)、嚥下障害の評価方法3)間接訓練の方法4)について述べてきた。嚥下訓練のなかで実際に食物を用いた直接訓練については他稿に譲り文献 5)6)の紹介にとどめることにして、本稿では鼻咽腔閉鎖不全に対して用いられるPLPについて述べてみたい。
はじめに
口腔領域の疾患の中でも鼻咽腔部の治療に歯科補装具が使用されるケースとしては、同部の組織欠損に適用される栓塞子(obturator)や口蓋形成術後に用いられる補綴的発音補助装置(一般的にはスピーチエイドと呼ばれるもの)などが鼻咽腔を補填するための装置であるのに対して、脳血管疾患および神経筋疾患にしばしば見られる嚥下障害(特に鼻咽腔閉鎖機能不全)の治療に用いられる歯科的補綴物をPLP(palatal lift prosthesis)といい、鼻咽腔閉鎖機能を賦活、獲得させるのが目的である。
鼻咽腔閉鎖メカニズムとは
ところで鼻咽腔閉鎖は、口蓋帆の後上方運動と咽頭側壁の内方運動などの協調運動からなるとされる7) が、これらの運動に関係する筋群の働きについて整理しておくことは嚥下メカニズムの理解を深める意味でも重要である。軟口蓋には5つの筋群がある。(1)口蓋帆張筋は耳管開口部を拡張させる(耳管を開ける)、(2)口蓋帆挙筋は口蓋帆を後上方に引く(軟口蓋を挙上)、(3)口蓋咽頭筋は口蓋帆を下制し、咽頭を収縮させ、(4)口蓋舌筋は舌背を挙上、(5)口蓋垂筋は口蓋垂を短縮し上方に引く。これらの筋群のうち、口蓋帆張筋だけが三叉神経(第5脳神経)の支配を受け、それ以外の筋群は、主に迷走神経(第10脳神経)由来の咽頭神経叢(第9〜10脳神経)の運動線維により支配されている。
さらにJOEL C.KAHANE7)は呼吸時と嚥下時では口蓋帆と咽頭側壁の運動様式に違いがあるとして、次のように述べている。「鼻咽腔閉鎖には、少なくとも2種の様式があることがわかっている。まず、発話時、ブローイング時、また口笛を吹くときでは(すなわち呼吸に関連した運動時)、口蓋帆と咽頭側壁に類似した運動様式がみられる。こうした運動時では軟口蓋は硬口蓋の高さもしくは硬口蓋より上方の高さで咽頭後壁に接するので、咽頭側壁の内方への運動範囲はこの領域までと限られている。これに対して、嚥下時や嘔吐時といった呼吸に関連しない運動時では、呼吸に関連した運動時とは様式が異なっている。こうした運動時では別の類似した様式が見られ、通常、口蓋帆は硬口蓋より下方の高さで咽頭後壁に接触するので咽頭側壁の運動範囲が拡大し、また咽頭のより多くの部分が運動する。」(以上文献7)より引用)
PLP、その効果と形態的特徴
嚥下障害患者にしばしば見られる麻痺性構音障害では、鼻咽腔閉鎖メカニズムをコントロールする神経機構(主に求心性には舌咽神経、遠心性には迷走神経)に問題が生じて、鼻咽腔閉鎖機能が不良となり鼻咽腔閉鎖不全となる。このような患者では呼気が鼻から漏れ、いわゆる開鼻声となったり、子音の発音が不明瞭になったり、食物が鼻から出てくるなど発音のみならず嚥下(食事)にも大きな影響を及ぼすことがよく知られている。このような鼻咽腔閉鎖不全を伴うケースに対して、PLP装着により鼻咽腔閉鎖機能および発語機能が70〜80%の割合で改善することが報告されている8)。山下8)は、PLPの治療効果は鼻咽腔閉鎖機能の改善だけではなく、発声発語機能および構音機能の改善と広範囲に及んでいると考え、その効果を高く評価している。
PLPは1958年GibbonsとBloomer によって考案されたもので、先天的組織欠損、CP、外傷、脳血管障害などによる鼻咽腔閉鎖不全のケースに使用される。本装置は表1に示したように硬口蓋を覆う床(硬口蓋部)の部分、軟口蓋を後上方に挙上するための挙上子(palatal
extension)と、これらをつなぐ連結部からなる。軟口蓋部には床を歯牙(大臼歯部)に固定するための維持装置が組み込まれているが、これには通常Adamsの
arrow-head claspが用いられる。軟口蓋の緊張が強く挙上に大きな力を必要とする時には小臼歯に単純鉤を補ってもよい。挙上子については研究者によりその形態は様々であるが、著者の制作方法では幅20mm、高さ15mmの半球状で厚みは約5mmとし、挙上子の後端は口蓋垂の基部に、その高さは上下的に軟口蓋が口蓋平面まで挙上して咽頭後壁に接触する位置とする。材料はオルソレジンRで制作する。
|
PLPの適応症について
次にPLPの適応症であるが、道ら9)の文献的考察によれば、Bedwinek and O`Brienは、構音器官の運動、発声、呼吸プロソディーの障害が軽度あるいは中等度で、学習意欲、家族の援助が平均以上で60歳以下の症例が適応であると報告し、Dworkin and Johnh は床の維持力の不足、軟口蓋の強い痙攣あるいは硬直、患者の協力不足などのある場合は不適応としている。Rosenbek and LaPointe は軟口蓋の痙攣の強い症例や無歯顎症例は不適応と述べているとされるが、著者のケースでは無歯顎でも作製した症例があるので不適応と一概には言い難く今後の検討課題と考えている。
|
表2に適応症について要点を整理してみたが、麻痺性構音障害患者では口唇、舌などの機能障害のほかに鼻咽腔閉鎖不全を伴うために発話明瞭度が著しく低下している場合が多く,開鼻声の改善は大きな目的となる。さらにこのような患者は脳血管障害等を基礎疾患として持っている場合が多く、観血的処置よりも保存的処置が望ましい。装置の制作上の問題として歯列の有無が装置の効果に与える点については、文献的に述べられている見解がそのまま成立するか否かについては今後の検討の余地があるのではと考えている。患者側の側面として装置の自己管理ができない場合は使用すべきではない。しかし、介護者等に対して装置の着脱などの訓練を十分に行い、第三者による管理ができる場合には当然使用すべきであろう。
PLPの調整について
PLP使用上の注意点であるが、装着直後には息苦しい(鼻閉感)、唾液が飲み込めない(嚥下困難)、異物感がある等の症状を訴えることがあるので事前にそのことを充分説明しておくことが望ましい。ただしあまり強調しすぎると使用を拒否する結果となることもあるので説明の際には装置の効果に力点を置くとよい。使用開始時には1回数分の短い装着時間とし、その後次第に時間を延長するようにしていくと違和感も次第に減少していく。症例により一概には言えないが、一月もすると、1日数時間の装着も可能となってくる。最終的には就寝中以外は装着を続けるようにしてもらう。摂食については、まずPLP装着の状態での飲水テストを行って液体の摂取を開始して、次第に食事を上げていき、固形物の摂食へと段階を進めていく。使用開始時の挙上子の位置(高さ)については、筆者の場合鼻息鏡をあて鼻からの漏れを調べ( /a/ を発声させる)、鼻息鏡の曇りのなくなる位置(挙上子の高さ)を確認して、その位置からいったん挙上子を下げて(つまり少し鼻咽腔の閉鎖を完全にはしない状態)、患者に鼻閉感が多少解消するのを確認した後にその高さを訓練の開始時の位置とするようにしている。
PLP制作上のポイント
PLPの制作は歯科で行う。まず、口腔内の印象であるがポイントとしては軟口蓋部の印象を採ることが重要であるため、二度印象採得を行う。一度目の印象では軟口蓋まで深めに印象すること、スタディモデルを作製する際には軟口蓋の印象面が表現された模型であることがポイント。さらにその模型上で個人トレイを作製するが、この際に模型の軟口蓋に相当する部分をほぼ硬口蓋の高さに一致させるようにトリミングしておく。さらにそのスタディモデル上で再度個人トレイを作製し、そのトレイを用いてPLPの本印象を行う。このようにして採得された模型は硬口蓋から軟口蓋へと緩やかな曲面を描くような形状となっている。この模型上でPLPの制作にかかる。模型で挙上子の位置を決めそのデザインを印記し、次にクラスプを屈曲しその脚を硬口蓋部に延長させ、さらに連結部も挙上子の中央から硬口蓋側のほうへ延長しておく。硬口蓋部に延長したそれぞれの脚部をオルソレジンを筆積み法で固定していく。最後に挙上子の部分の作製であるが、著者の制作方法では幅20mm、高さ15mmの半球状で厚みは約5mmとし、挙上子の後端は口蓋垂の基部に位置するようにしている。先に紹介した道ら9)の文献的考察によれば、この挙上子の位置、大きさ、挙上の圧などの決定は臨床的な勘に頼っているのが現状として、Schweigerらの挙上子の後縁は口蓋舌弓と口蓋咽頭弓の間の半月ひだの部位までとする考え方、Ramseyらの挙上子の矢状断面形態をアーチ型とし、辺縁形態は口蓋垂基部に切痕を付けたハート型とする考え方などを紹介している。
今回は主にPLPについてその意義、適応症、使用上の注意点、制作上のポイントについて述べた。
まだ概念や術式が確立していない領域も残されているようなので、読者の今後の取り組みに期待してこの稿を終わりたい。
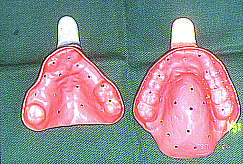 図1 PLPのための印象用個人トレイ (右が本印象用) |
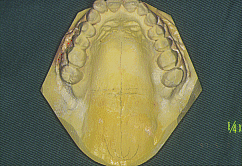 図2 個人トレイで印象した石膏模型 (軟口蓋の部分をトリミング) |
 図3 オルソレジン |
 図4 オルソレジン(筆積み法) |
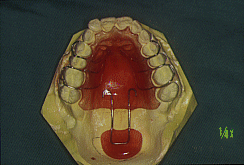 図5 PLPの咬合面観 |
 図6 PLPの側面観 |
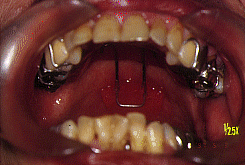 図7 口腔内に装着されたPLP |
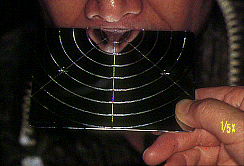 図8 PLP装着直後の鼻息鏡所見 |
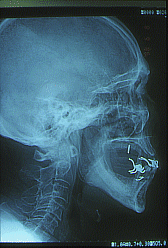 図9 PLP装着前のX線像 |
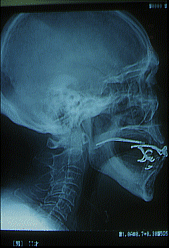 図10 PLP装着後のX線像 (軟口蓋が後上方に挙上されている) |
参考文献
- 山部一実:嚥下障害へのアプローチ(1)。月刊保団連、567:57-60、1998
- 山部一実:嚥下障害へのアプローチ(2)。月刊保団連、575:61-64、1998
- 山部一実:嚥下障害へのアプローチ(3)。月刊保団連、581:77-80、1998
- 山部一実:嚥下障害へのアプローチ(4)。月刊保団連、585:61-64、1998
- 清水充子:直接的訓練。中部摂食・嚥下リハビリテーションセミナー記録集、 中部摂食・嚥下リハビリテーション研究会、1998
- 金谷節子ほか:摂食・嚥下障害への営養科的アプローチ。臨床リハ、6(7)、1997
- JOEL C.KAHANE著 新見成二監訳:発話メカニズムの解剖と生理。インテルナ出版、 1998
- 山下夕香里、今井智子:鼻咽腔閉鎖障害機能不全をともなった後天性運動障害性構音障害患者における軟口蓋挙上装置の効果、聴能言語研究、7、1990
- 道 健一ら:後天性運動障害性構音障害に対する軟口蓋挙上装置(Palatal lift prosthesis)の使用経験、音声言語医学、29:239-255、1988
| アプローチ(1) | アプローチ(2) | アプローチ(3) | アプローチ(4) | アプローチ(5) |